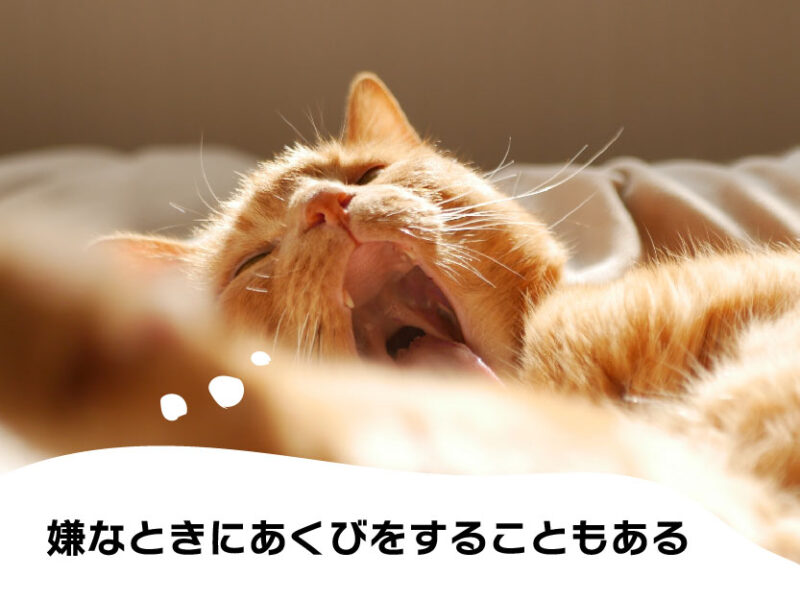2025.11.10
猫のあくびが多い理由は?病気・ストレスではないの?
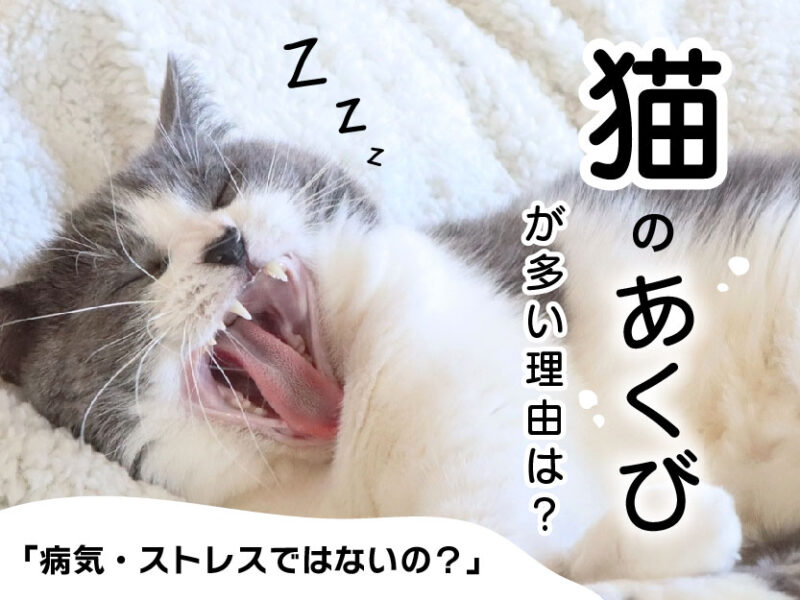
猫が1日でするあくびの回数は人間よりも多いとされます。
人間の場合は眠たいときや疲労を感じたときに出やすいですが、
猫はさまざまなケースでするので、あくびが多くなりやすいです。
では、どんなときにあくびをするのか、病気やストレスについても紹介します。
ほとんどの場合は生理現象のあくび
猫はあくびが多いですが、そのほとんどは生理現象です。
日常的に出るので、こういった状況であればとくに気にする必要はありません。
眠たいとき
人間と同じで、猫も眠気を感じるとあくびが出やすいです。
眠たいときは副交感神経が優位になり、脳の酸素が不足しやすいです。
あくびをすると口を大きく開けて呼吸をすることになるので、無意識に多くの酸素を取り入れられます。
そのため、眠気を感じると生理現象であくびが出やすくなります。
猫は1日12~16時間ほど寝ますが、人間のように長時間眠り続けるわけではありません。
短いときは15~30分ほどの睡眠を何度も繰り返すので、人間よりも眠気を感じる回数が多くなり、あくびの回数も多くなりやすいです。
寝床にいるとき、ウトウトしているときなど、何度もあくびをするのであれば、眠気を感じている可能性が高いです。
ゆっくり眠れるようにそっとしておいてあげましょう。
リラックスしているとき
眠たいときと同じで、リラックス状態のときも、副交感神経が優位になって生理現象のあくびが出やすいです。
猫同士のあくびは、争う気はないという意思表示。
リラックスした気持ちを相手に伝えるための手段のひとつだとされます。
飼い主さんを見たり目が合ったりしたときのあくびも、リラックス状態を伝える合図だと考えられます。
様子を見ながら、優しく言葉をかけたり撫でたりしてあげましょう。
甘えているとき
甘えたいときや嬉しいときも、あくびをしやすいです。
細目で見つめながら、喉を鳴らしながら、スリスリしながらなど、猫がよくする甘え仕草と一緒にあくびをすることも。
目の前で寝転んでアピールしたり、チラチラ見てきたりと、構って欲しい仕草もしているのであれば、甘えたくてあくびをしている可能性が高いです。
あくびをしながら鳴くのは、コミュニケーションのひとつだとされます。
喉や声帯が開いて自然に声が出ることもありますが、甘えたり要求したりするときに見られやすいです。
また、猫は記憶力が優れており、幸せや恐怖などの感情と結びつく記憶は長く覚えているとされます。
過去にあくびをして構ってもらえた経験から、甘えたくなるとあくびを繰り返すことがあります。
体にスイッチを入れるとき
猫にとってのあくびは、活動前のスイッチとしての役割もあります。
猫には、休憩モードと活動モードがあり、1日の中で何度も切り替えているとされます。
睡眠・休息をしているときは休息モードになり、狩り・遊び・食事などのときは活動モードに切り替わる仕組み。
モードを切り替える方法はいくつかあり、あくびもその中のひとつです。
動く前にあくびをして、脳に酸素を取り入れたり血行促進をしたりし、準備運動をするという流れ。
同じネコ科のライオンなども、狩りを始める前にあくびが多くなることが確認されています。
寝起きや、食事・運動・爪とぎなどをする前にあくびをするのであれば、体にスイッチを入れている可能性が高いです。
猫にとって伸びも活動前のスイッチのひとつなので、屈伸とあくびを一緒にすることも多いです。
嫌なときにあくびをすることもある
猫のあくびはほとんどの場合で生理現象ですが、ポジティブな意味合いばかりではありません。
動揺したりストレスが溜まったりしたときも、猫によってはあくびをします。
気持ちを落ち着かせるため
あくびにはさまざまな意味があり、気持ちを落ち着かせる役割もあります。
猫は、転位行動をする動物です。
転位行動とは、ネガティブな感情になったときに、関係ない行動をして気持ちをリセットする仕草のこと。
具体的には、ジャンプを失敗したり驚いたりした後に、あくびして動揺を落ち着かせようとします。
毛づくろいや爪とぎも猫がよくする転位行動のため、あくびと一緒にすることもあります。
人間でいうと、頭をかいたり貧乏ゆすりしたりするようなもので、そこまで深刻ではないことが多いです。
気を紛らわせてクールダウンしようとしているので邪魔せずにそっとしてあげましょう。
不満があるとき
ストレスや不満を感じているときも、あくびをすることがあります。
猫はもともと単独行動でマイペースな動物のため、ストレスに強くありません。
触って欲しくないときに触る、音がうるさい、寝ているのを邪魔された、叱られたときなど、ストレスを感じるとあくびをして気を紛らせることも。
撫でているときにリラックスしてあくびをすることもありますが、触られて嫌なときにもするので、愛猫の気持ちを察しましょう。
尻尾を床に叩きつけたり、鋭い目をしたり、耳を伏せたり、飼い主から離れるなども見られるときは、不満を感じている可能性が高いです。
猫が不満を感じてあくびする頻度や回数が多いのであれば、生活環境や接し方を改善してあげましょう。
あくびと関わりがある病気やトラブル
猫のあくびそのものと病気は関係ありません。
愛猫のあくびが多いだけであれば病気の可能性は低いですが、他の症状もあるときは注意しましょう。
異物の誤飲
猫が異物を誤飲すると、何度もあくびをすることがあります。
喉に詰まったり食道を圧迫したりすると違和感があり、吐き出そうとします。
ストレスからあくびを何度もすることもあれば、口を大きく開ける仕草があくびのように見えることも。
何度も苦しそうな様子であくびをしたり、嘔吐を伴うあくびをしたりするのであれば、誤飲した可能性があります。
その他、食欲不振や元気のなさ、よだれやくしゃみ、息が荒いなどの症状がでることが多いです。
誤飲した物によっては命の危険もあるので、症状があればすぐに動物病院に行きましょう。
気管に詰まることがあるので飼い主さんが取ろうとはせず、獣医師に任せるようにしてください。
口の中のトラブル
猫の口の中にトラブルがあっても、あくびが多くなるわけではありません。
しかし、あくびの臭いが気になることがあります。
口内炎や歯周病が原因であくびが臭いときは、アンモニア系の臭いがしやすいです。
炎症を起こして赤くなったり、よだれが出たり、食欲減退などが現れやすいのも特徴。
あくびをしたときや食事をしたときなど、口の中を気にする素振りをしやすいので、様子がおかしくないか確認しましょう。
食事後はフードの臭いがして分かりにくいため、時間が経ってから確認してください。
内臓などの病気や疾患
内臓などの病気や疾患があると、あくびが臭ったり回数が多くなったりすることがあります。
腎臓病は、口から嫌な臭いを発しやすく、あくびをしたときにアンモニア臭がしやすいです。
食欲減退や嘔吐、多飲多尿、体重減少などの症状もでやすいです。
脳への血流不足や酸素欠乏、脳腫瘍などがあると、あくびの回数が多くなることがあります。
あまりにもあくびの頻度が多く、元気・食欲・呼吸などに異常があるときは注意。
いずれにしても、ただあくびが多いだけであれば問題ないことが多いですが、他の症状もあるときは念のために検査を受けましょう。
まとめ
猫は、眠る時間が長くて眠気を感じやすく、リラックスや気持ちの切り替えなど、さまざまな状況であくびをします。
猫は人間よりもあくびをする状況が多いため、そのぶん回数が増えるのは自然なことです。
ほとんどは生理現象なので心配ありませんが、異常があるときは動物病院に連れて行きましょう。