2025.09.13
犬が誤飲!うんちで出る大きさは?何日で出る?

犬は好奇心が旺盛で、気になるものを口に入れて確かめようとします。
口に入れたり噛んだりして確かめるのは本能のひとつともされているため、誤飲に悩まされる飼い主さんも。
誤飲してからそう時間が経たないうちに排泄されることもあれば、なかなか出ないこともあります。
犬が誤飲してうんちで出る大きさ、かかる時間、病院に行くかどうかなどを知っておきましょう。
うんちで出るときの目安とポイント

食べた異物が胃に残ったままになるのはまれであり、ほとんどが腸へ流れていきます。
しかし、どんな物でもうんちとして出るわけではないため、出る大きさや形、出るまでにかかる時間などの目安を見ておきましょう。
犬が誤飲したときにうんちで出る大きさ
うんちで出る大きさのひとつの目安が2cmです。
1cmほどの小さな異物であればそのままうんちとして出ることが多く、2cmだと物によっては詰まることがあり、3cm以上になると腸などに詰まる可能性が高くなるとされます。
犬の消化管の大きさは人の指ほどだとされているため、2cm以内かどうかを目安にしましょう。
ただし、小さい異物であれば必ずうんちとして出るわけではなく、犬の体の大きさによっても異なります。
小型犬は体が小さいため、食道や腸もそのぶん狭いです。
体が小さければ小さいほどうんちで出にくいため、チワワやトイプードルなどの超小型犬の場合はより注意しましょう。
うんちで出やすい形や素材
異物の大きさだけではなく、形や素材によっても出やすいかどうかが異なります。
たとえば、小さいボタンのような丸い物や、凹凸のないツルツルした素材などは、消化管を流れやすいため、うんちとして出てきやすいです。
逆に、串などの尖った物や表面がザラザラした物などは流れにくいですし、ビニールやひも状などの長さがあるものは胃や腸に絡まりやすいです。
また、プラスチックは表面がツルツルしていますが、噛みちぎることで鋭利になって出てこないことも。
うんちとして出るかどうかは形状や素材にもよるので、飲み込んだ物をしっかりチェックしましょう。
犬が誤飲してうんちで出るまでの時間
どれくらいの時間でうんちとして出るのかは、飲み込んだ異物によって異なります。
一般的な目安は1~3日ほどで、場合によっては3日以上経ってから出ることもあります。
通常の食べ物であれば半日~1日ほどで出ます。異物はうまく消化できないため、うんちとして出るまでより多くの時間がかかりやすいです。
しかし、一週間経ってもうんちが出ないのは時間がかかりすぎです。
体内で詰まっている可能性が高くなるため、すぐにでも動物病院で診察を受けましょう。
状況に関係なく動物病院に行ったほうがいい理由

犬が誤飲したものがうんちで出る大きさだから安心、元気そうだから問題ないというわけではありません。
犬は言葉で伝えることができませんし、こういった理由から、状況に関係なく動物病院へ行きましょう。
うんちで出ても100%安心はできない
数日後にうんちで出ればもう安心かといえばそうではありません。
うんちで出たということは、確実に誤飲をしていたということです。
犬は噛みちぎって誤飲することがあるため、まだ異物が胃などに残っていることがあります。
また、すべて出たとしても異物によって消化管が傷付いていることもあります。
愛犬が元気でも、まだ体内に残っていたり、数日経ってから急に症状が出てきたりすることがあるので、動物病院へ行っておくと安心です。
様子を見るよりも動物病院に行ったほうが早い
犬が誤飲した場合、何日も様子を見るよりも動物病院に行ったほうが早いです。
長ければ、うんちで出るまで3日ほどかかったり、症状が出るまでに数日かかったりすることも。
誤飲したかわからない、うんちで出ないが元気、うんちは出るが異物が入ってないなど、ケースはさまざま。
どのケースでもずっと心配をしなければならないため、気持ち的にも診察を受けた方が安心です。
不在にしているときに症状が出たり、いざ様子がおかしいときに診療時間外だったりすることもあるので行けるときに行きましょう。
最悪の場合は命を落とすことがある
食べることができたサイズのものが胃に残ったままになるのはまれですが、実際に死亡例もあります。
犬が誤飲しやすいのが、ひも状の物、竹串、布、ボール、プラスチックなどです。
消化管が詰まって腸閉塞になったり、腸に穴が開いて腹膜炎を引き起こしたりすることで死亡した例があります。
また、玉ねぎやチョコなど、有害なものを誤飲したときは中毒症状を起こすことがあります。
犬が誤飲してうんちで出る大きさであったとしても、物によっては命を落とすため、検査を受けておきましょう。
犬が誤飲したときの対処法と注意点
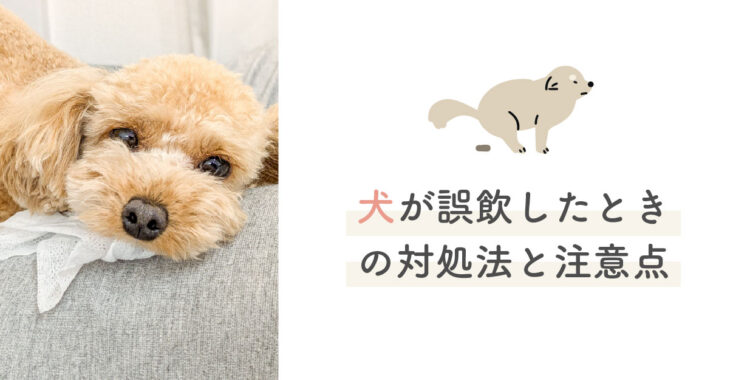
愛犬が誤飲した可能性があるときは、状況を把握してから動物病院に連れて行くことが大事です。
逆効果にならないように注意点も含めて紹介していきます。
できるだけ状況を確認する
動物病院で正確に診察してもらうためにも、愛犬の状態を把握するためにも、できるだけ状況を確認しましょう。
まずは犬が何を誤飲したのか、どれくらいの量か、何時ごろに食べたのかなど、分かる範囲でチェックします。
噛みちぎった現物があるときは捨てずに持っておき、写真も残しておきましょう。
現物や写真を残しておくと、うんちで出てきたときに比べやすく、獣医師も正確な判断がしやすくなります。
症状があるかどうか確認する
誤飲してもまったく症状がないこともあれば、さまざまな症状が出ることもあります。
たとえば以下のようなことがないか確認しましょう。
●下痢
●よだれ
●食欲不振
●元気のなさ
●呼吸の異常
●腹部の違和感
上記のような症状があれば、腸閉塞の可能性があります。
腸閉塞とは、誤飲によって腸が詰まることです。
組織が腐ったり、腸管が破れたり、脱水症状を引き起こしたりする命に係わる疾患です。
誤飲の症状がないよりもある方が危険性が高いため、愛犬の様子がおかしくないか確認しましょう。
無理に吐かせようとしない
異物を無理に吐かせようとすると、よけいに危険を招く恐れがあるので止めておきましょう。
動物病院で嘔吐処置をすることもありますが、注射の嘔吐薬を使うのが一般的。
正しくない方法で吐かせると、異物を吐く過程で消化管を傷付けたり、気管に入り込んで肺炎を起こしたりすることがあります。
まだ飲み込んでいないときは無理に止めず、オヤツなどを出して気をそらしましょう。
誤飲しやすい犬のタイプ

誤飲しやすいとされている犬のタイプは以下の通りです。
●食欲旺盛
●1歳未満の子犬
●しつけがされていない
犬は人間のように手が使えないため、口に入れたり噛んだりして物を確かめることがあります。
好奇心が旺盛だとさまざまな物に興味をもち、誤飲しやすくなります。
食欲旺盛な犬も、食べ物の匂いがついた串や包装などを飲み込んでしまいやすいです。
子犬は成長過程のため、周りにあるものを噛んだり舐めたりしてさまざまなことを学んでいきます。
しつけがされていない犬は、していい事と、してはいけない事の判断がつきにくいです。
こういった犬の場合、何度も繰り返すことがあります。
誤飲しそうなものは片付ける、食べ物や匂いのついたものは隠す、ゴミを漁ったら叱るなどして誤飲のリスクを減らしましょう。
まとめ
犬が誤飲してうんちで出る大きさは2cmほどとされます。
愛犬がいつも通りであれば安心しますが、
場合によっては、吐かせたり処置が必要だったりすることも。
元気かどうか、うんちで出たかどうかに関係なく、念のために動物病院に行きましょう。

監修者
獣医師 小川篤史
明石・西明石の動物病院「こすもす動物診療所」院長
(宮崎大学農学部獣医学科卒業・明石市獣医師会所属)
兵庫県加古川市の動物病院に勤務後、兵庫県明石市に「こすもす動物診療所」を開院。
犬や猫、小動物を中心に診療・予防医療を行う。


