2025.08.07
犬がチョコを食べた!中毒症状が出る時間・量・応急処置は?

チョコレートは甘くて良い香りがしますし、犬は飼い主が食べているものに興味をもちやすいです。
鼻が利くので、隠していても自分で見つけてこっそり食べてしまうことも。
犬がチョコを食べたときに飼い主さんができることや対処法、注意点も見ておきましょう。
犬がチョコを食べたらどうなる?危険な理由と症状

チョコは犬に有害な成分が入っている
チョコは人間用に作られたものなので、犬の体には良くありません。
チョコには脂質や糖質、テオブロミンなどが含まれています。
脂質や糖質は犬にも必要な栄養ですが、量が多いため、健康被害を与えやすいです。
テオブロミンはカカオ豆に含まれている成分で、犬には有害。
人間にとってはリラックス効果などをもたらす成分として知られますが、犬は分解する力が弱いため、中毒症状を引き起こすことがあります。
テオブロミンの血漿中半減期は、ヒトと比較して著しく長い(17.5時間、ヒト:6―10時間)
犬はテオブロミンの排泄速度がかなり遅いため、中毒になりやすい
―与えてはいけないたべもの その2:チョコレート
カカオの濃度が高いとテオブロミンの含有量が多くなりやすいです。
もちろん個体差がありますが、「カカオ70%配合」などのカカオ濃度が高いチョコを食べたり、大量に食べたりするとより危険性が高くなります。
【参考:チョコレートのテオブロミン含有量(mg/g)】
| ホワイトチョコレート | 0.009~0.035 |
| ミルクチョコレート | 1.5~2.0 |
| 中甘ダークチョコレート | 3.6~8.4 |
| ビターチョコレート | 12~19.6 |
犬がチョコを食べたときの中毒症状
カカオに含まれる成分「テオブロミン」によってこのような中毒症状を引き起こすことがあります。
●嘔吐や下痢
●失禁
●呼吸が荒い
●震え
●けいれん
水をたくさん飲む、下痢や嘔吐、落ち着きのなさなどは初期症状とされます。
しばらくすると回復し、何事もなかったかのように元気になることもあります。
回復せずに症状が進行した場合、呼吸の異変や震え、けいれんなどが起こり、重症化することがあるので注意。
数は多くありませんが、症状が進行したのちに死亡した例や、肝臓などに後遺症が残った例もあります。
犬がチョコを食べたときに知っておくべきこと

犬がチョコを食べたからといって、必ず中毒症状が出るわけではありません。
まったく様子が変わらないこともありますが、時間が経ってから症状が出ることもあります。
食べてから中毒症状が出る時間
犬がチョコレートを食べて中毒を起こす場合、時間が経ってから症状が出ることが多いです。
個体差がありますが、症状が出る目安の時間は4~12時間ほど。
食べた直後はいつも通り元気であっても、数時間後に嘔吐や下痢などの初期症状から始まり、重症化することがあります。
まれに数日後に症状が出ることもありますが、24時間経っても元気で異変がない場合は、そのまま症状が出ることなく治療が必要ないケースが多いです。
中毒症状が出やすいチョコの量
チョコを食べた量が多ければ多いほど、中毒症状を起こす可能性が高くなります。
あくまで目安ですが、2kgの犬が一般的な板チョコを食べた場合、ミルクチョコは4分の1、ビターチョコは20分の1ほどで症状が出始めるとされます。
ホワイトチョコは製造過程の問題でテオブロミンがほとんど含まれていないため、中毒を起こす可能性が低いとされます。
許容量は体重によっても異なり、小型犬は大型犬よりも中毒を起こしやすいです。
症状が出るかどうかは個体差があるため、しっかり様子を観察してください。
犬がチョコを食べたときの対処法と注意すべきこと
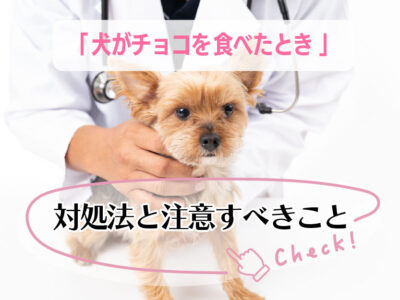
愛犬がチョコを食べてしまったときは、慌てずに対処しましょう。
よかれと思ってしたことが逆効果になることもあります。
自宅でできる応急処置はない
基本的には、飼い主さんが自宅でできるような応急処置はありません。
塩やオキシドールを飲ませて吐かせる方法が紹介されていることがありますが、悪影響を及ぼす可能性が高いです。
食塩中毒になったり胃腸を傷つけたりしやすいので止めておきましょう。
また、無理に水を飲ませるのも危険です。
犬が自分で水を飲むのは問題ありませんが、無理に飲ませると誤嚥してしまう可能性があります。
自己判断で応急処置をすると逆効果となり、新たな問題が発生しやすいので止めておきましょう。
すぐに動物病院に連れて行く
犬がチョコを食べたときは、すぐに動物病院に連れて行ってください。
状態に応じて、催吐処置を行ったり、薬や点滴を使ったりして治療を行うので、獣医師の判断に任せましょう。
犬がチョコレートを少量しか食べてないときや、食べたかもしれないとき、症状がないときも、念のために連れて行くと安心。
食べてからさほど時間が経っていない場合は、薬を使った催吐処置を行うのが一般的です。
しかし、食べてから時間が経っている場合は、全身麻酔をして胃洗浄をしなければならないケースもあります。
どのような治療を行うのかは状態によりますが、愛犬の負担を減らすためにも、早めに動物病院に連れて行きましょう。
パッケージや食べた量を確認する
動物病院での診察をスムーズにしたり、正しく診断したりするためにも、犬が食べたチョコのパッケージを保管しておきましょう。
チョコの種類によって危険度が変わることがあるので、動物病院に行くときはパッケージを持参してください。
何時ごろにどれくらいのチョコを食べたのかも含めて、分かる範囲でメモしておきます。
犬が吐いたり下痢をしたりする場合は、念のためにラップなどに包んで持っていきましょう。
チョコを口にするのを見ても慌てない
犬がチョコを食べている最中だった場合は、慌てずに落ち着いて対処してください。
大きな声を出したり怒ったり、無理矢理チョコを口から取ろうとすると、驚いて飲み込んだり、急いで食べたりすることも。
ドッグフードやオヤツを出して興味を引くなどし、食べるのを止めさせましょう。
カカオが使われている食べ物は隠す
犬がチョコを食べて中毒を起こす主な原因は、カカオに含まれるテオブロミンという成分です。
カカオから作られるココアやカカオバターなどにもテオブロミンが含まれており、ゼリーやクッキーなどのお菓子にも使われていることがあります。
いくら少量であっても犬に良くない成分なので、冷蔵庫の中や鍵つきの棚など、愛犬が食べないように対策してください。
まとめ
犬がチョコを食べたときは、自宅での応急処置はせずに動物病院に連れて行きましょう。
少し食べただけであれば問題ないこともありますが、体が小さい小型犬は少量でも症状が出ることがあります。
時間が経ってから症状が出やすいため、診察時間のことも考え、行けるときに診てもらいましょう。

監修者
獣医師 小川篤史
「こすもす動物診療所」院長
(宮崎大学農学部獣医学科卒業・明石市獣医師会所属)
兵庫県加古川市の動物病院に勤務後、兵庫県明石市に「こすもす動物診療所」を開院。
犬や猫、小動物を中心に診療・予防医療を行う。


